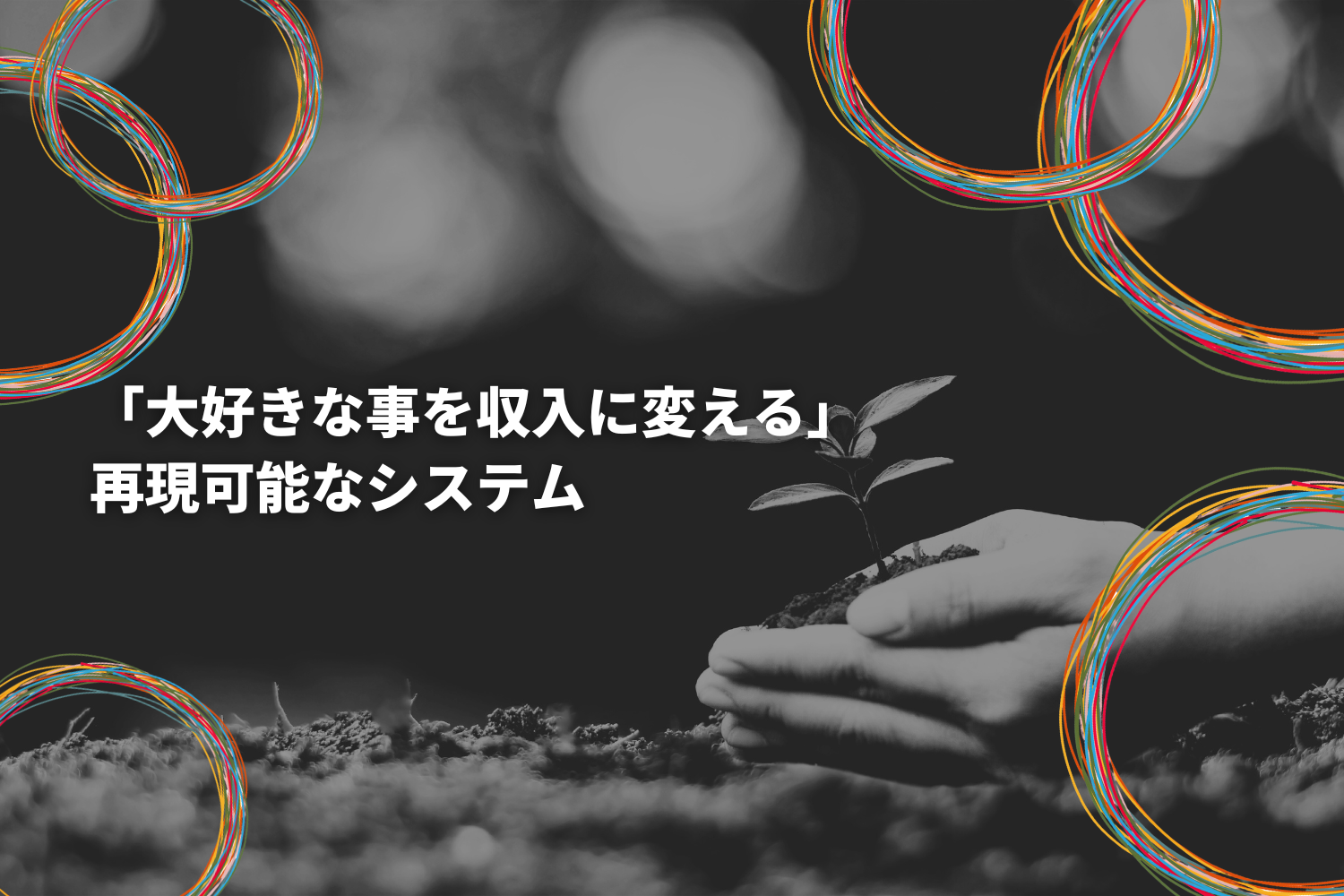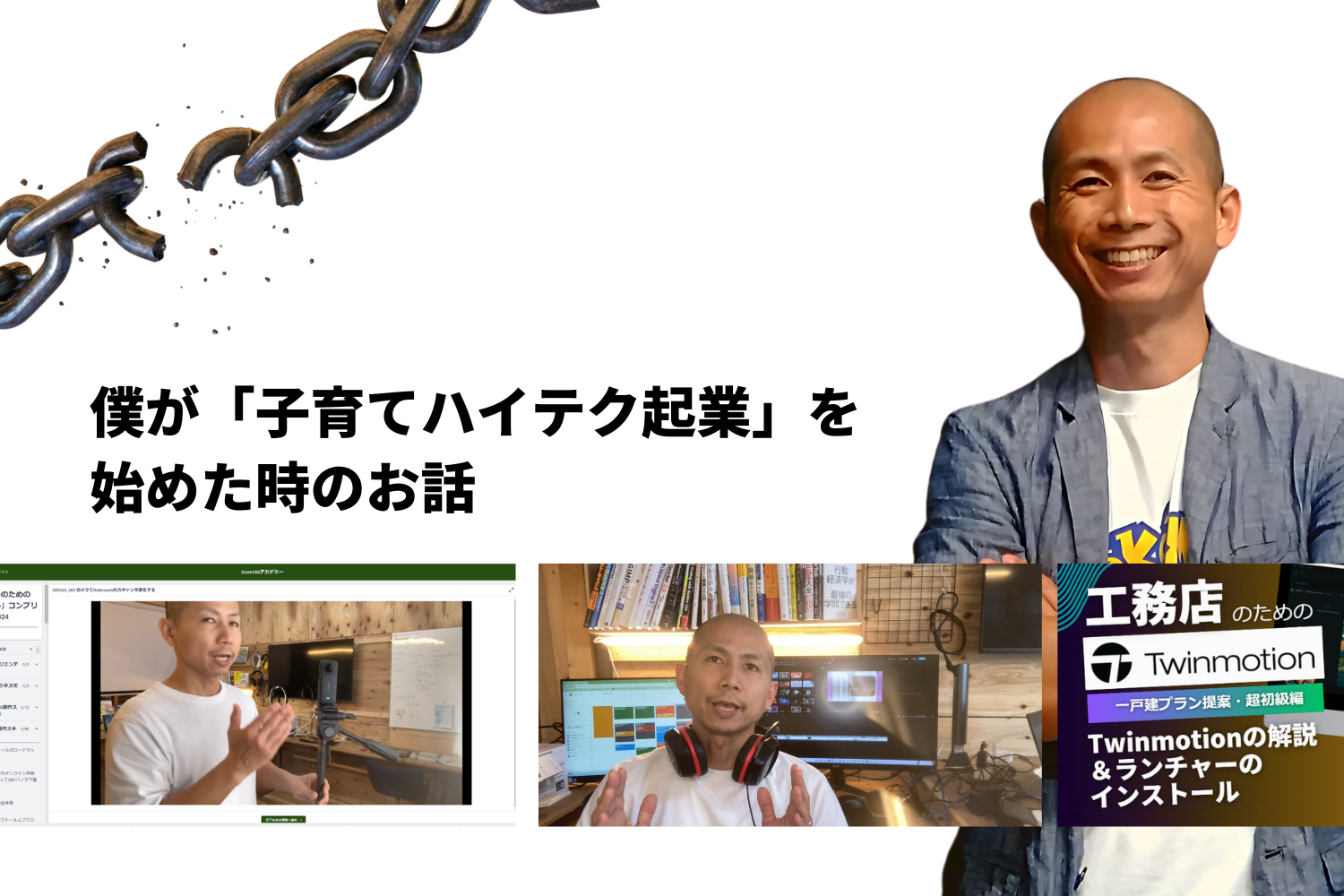私が最初に売ったVR制作サービス
こんにちは、360 ACADEMYの椙原俊典(すぎはらとしみち)です。
まず、僕が最初に考えついて売り出そうと決めたVR製作サービスについて、具体的な経緯をお話します。
僕が広告代理店に事業リーダーとしてのオファーを受ける直前のお話。
派遣社員として製造業の現場で僕が試行錯誤していたことは、360度カメラを使用して工場やプラント、実験装置などの空間を撮影し、それをストリートビューのようなVRコンテンツにすることでした。
この手法は「バーチャルツアー」や「パノラマツアー」と呼ばれ、当時のVRコンテンツとしては、ごく基本的なものでした。
現在では、アバターを用いたメタバースのようなVR空間も一般的になっていますが、当時はまだストリートビュー方式の360度映像が主流でした。
僕は工場の中を360度カメラで撮影し、それをVRコンテンツにする技術を身につけたことで、これを何とか販売して自分の生計を立てたいと考えました。
そこで最初に考えたのは、この技術を誰かに教えることでした。
当時、僕はオンラインで教育コンテンツを販売する「オンラインコースビジネス」について研究していたからです。
動画を撮影してオンラインで収入源をつくるというスタイルが自分に合っていると感じたからです。
オンラインコースビジネスとは、もしあなたが360 ACADEMYで僕のオンライン授業を受けた事があれば、あれです。
自分が誰かに教えたいと思う事を文章、動画などにしてオンラインのプラットフォームを使って提供するビジネスです。
僕は住宅会社の設計者、営業担当者をターゲットにしようと考え、「工務店のためのVR製作」講座を作成しました。
しかし、このコースは当時ほとんど売れませんでした。
正確に言えば「売り方が分からない」という状況でした。
広告費を使ってWEB広告を出す余裕なんてない状況で、オンラインで会ったこともない人に、自分の動画授業にお金を払ってもらうなんて、途方もない事のように感じられたのを覚えています。
しかし、とにかく何か行動を起こそうと、YouTubeに動画授業の一部をアップしてPRを試みましたが、チャンネル登録者や「いいね」の反応、役に立ったというメッセージを頂くことはあったものの、実際に収益化することはできませんでした。
そこで、僕はターゲットの視点を変え、個人向けのVR製作講座を一旦保留にしました。
その代わりに、不動産会社や住宅会社、建築会社の経営者向けに「御社でVRのモデルハウスを導入しませんか?」という製作代行サービスにアイデアを切り替えたのです。
その経緯については、別の記事で広告代理店の持つ既存のコネクションを活用しようとアプローチしたことを紹介しました。
ここで重要なのは、同じVR製作スキルをからスタートして、最初は「個人に教える」形でビジネス展開を試みたものの、思うように成果が出ず、次に「事業者向けに代行する」形に変更したことで、売れるようになったという事です。
重要なのでもう一度繰り返します。
「個人」×「教えます」から、「事業主」×「代行します」です。
当時はまだ「VRで住宅会社のモデルハウスを作る」という概念が一般的ではなかったため、自ら学びたいと考える潜在的な需要が少なく、私の情報を検索するのは一部の海外のマニアックなツールを調べている人に限られていました。
結果として、「VR製作を学びませんか?」というアプローチでは反応が薄かったのです。
しかし、住宅関係の会社の経営者の方たちは、家がなかなか売れないという共通の悩みを抱えていました。
私はその普遍的な課題に対し、「VRのモデルハウスを導入すれば、今よりも家が売れるようになります、その理由は、、、」と訴えかけ、売り方を変えたのです。
この気づきこそが、私が停滞した状態から次の段階に進むための鍵となりました。
誰に売るのか?それが問題だ
どんな場合でも、事業主、つまり社長に対して「何かを代行します」というアプローチが最適とは限りません。
しかし、当時の僕のように、あるいは今のあなたのように、なるべく少ない時間と労力でより単価の高い仕事を安定して得ようと考えた場合、個人に何かを売るという発想はあまりお勧めできません。
その理由は、個人が支払える金額には限界があるためです。
一方で、経営者にとって会社の売上や利益を伸ばし、新規顧客を獲得することは最重要課題であり、そのためにコストを投資しています。
実際に、日本の中小企業庁の統計によれば、中小企業の倒産理由の約7割は販売不振、つまり「モノが売れない」ことに起因しています。このような状況下で、「販売促進のためのVR活用」という切り口で提案すれば、個人に向けたアプローチよりも高い確率で受け入れられるのです。
ここで、マーケティングに関する重要な概念を再確認しましょう。
ドラッカーの言葉にあるように、「マーケティングの目的は販売を不要にすること」です。
これは「何を売るか」だけでなく、「誰に」「どのように売るのか」といった要素の組み合わせも含め、全体の最適化が重要であることを意味しています。
最初に私が「個人向けに教える」選択をしたのもマーケティングの一つの選択肢ですが、「事業者向けに代行する」というアプローチの方が高確率で売れる結果につながったのです。
そして、1案件ごとの単価も、当然数千円ではなく、数十万円になりました。
個人がスキルアップのためにお小遣いから捻出できる金額と、企業の広告費とでは桁が違うのは当然です。
改めて強調したいのは、フリーランスを目指す際、最初のステージでは時間が最も不足する資源であるということです。
仕事を掛け持ちしたり、長時間労働で疲れ果てたりする中で、小さな仕事を多数こなすことは難しいでしょう。
だからこそ、一つの取引でより高い金額を支払ってもらえる相手を選ぶことが重要です。その解決策の一つが、事業主をターゲットにすることなのです。この「誰に売るか」という視点を、ぜひ覚えておいてください。
経営者の課題解決を売るというビジネスモデル
では、ここからは再現性のあるビジネスモデルを構築するために、経営者の課題解決についてもう少し深掘りして考えてみましょう。
まず、経営者が自社の事業に対してさまざまな課題を抱えていることは明白ですが、その課題をより深く理解する必要があります。
なぜなら、「経営の課題を解決します」という漠然としたアプローチでは、抽象的すぎて頼りないからです。
例えば、戦国時代の戦いにおいて、小さな軍が大軍に挑む際に「錐形(すいけい)」という陣形を用いる場面を見たことがあるかもしれません。
錐形とは、錐(キリ)のように尖った陣形で相手の防御を貫く戦術です。
この錐形の陣形と同様に、少ない時間・資金・労力で相手に仕事を売り込むには、特定のポイントを鋭く尖らせる必要があります。
つまり、「経営の課題を解決します」という広範な主張ではなく、より具体的に課題を絞り込むことが重要です。
では、経営の課題にはどのようなものがあるでしょうか?
先ほどお話しした「販売不振」がまず挙げられます。
しかし、それだけではありません。
経営者は以下のような課題を抱えています。
1.新規集客の課題:新しいお客さんを集められない。
2.販売の課題:お客さんが集まっても成約にならない。
3.人手不足や採用の課題 :適切な人材を確保できない。
4.人材育成の課題: 採用した人材が短期間で離職してしまう。
5.業務効率化の課題 :無駄な会議や業務フローによる無駄。
6.デジタル化の課題 – デジタルが進まず、時代遅れな仕事の進め方を脱却できない。
これらの課題は特定の業界に限らず、あらゆる業種に共通して存在します。
したがって、僕たちはまず、これらの課題のうちの一つにフォーカスし、
「私はあなたの○○の問題を解決する専門家です」と自己紹介できるようにする必要があります。
最初は一つの課題に特化することで、相手にとってより信頼感のある存在となることができます。
そして、後に経験を積めば、複数の領域にまたがった解決策を提供することも可能になります。
しかし、最初の段階では「尖らせる」ことが重要です。
さらに、もう一つ重要なポイントがあります。
それは、「業界や業種を特定する」ことです。
例えば、私の場合、あらゆるビジネスモデルの「販売不振」をVRで解決するのではなく、不動産・建設業界に特化して「VRモデルハウスを活用した販売促進」という形で尖らせました。
これにより、僕の提供するサービスが、一般的な集客コンサルタントや販売システムを扱う企業とは一線を画すものとなりました。
例えば、あなたが工務店の経営者で、住宅がなかなか売れない状況にあるとします。
以下の二人の専門家がいた場合、どちらに相談したいと思うでしょうか?
(1人目の専門家)
業界を問わず幅広い分野で活動している集客コンサルタント(テレビCM、Web広告、SNS運用など幅広く対応可能)
(2人目の専門家)
工務店向けに特化した集客・販売専門家(VRを活用した具体的なソリューションを提供)
多くの経営者が、より自社のニーズに合った後者を選ぶでしょう。
このように、ターゲットを「課題」と「業界」によって絞り込むことで、顧客にとって選びやすく、唯一無二の信頼される存在となるのです。
まとめると、再現性のあるビジネスモデルを構築するためには:
1.経営課題を具体的に分類し、その中の一つにフォーカスすること。
2.業界を特定すること。
これらの要素を掛け合わせることで、あなたにとって強力な武器(商品・サービス)が出来上がります。
テクノロジーの力で解決策を生み出す
ここまでの内容を振り返ると、僕たちは「経営者の特定の課題を解決する専門家」となることで、子育てと両立できるビジネスを始めるべきだというスタート地点に立ちました。
次に考えるべき課題は、「どのようにしてその特定の課題を解決するのか」、つまり 解決策を生み出すプロセス についてです。
いくら課題を特定できても、解決策のプロセスに 再現性 がなければ、ビジネスは安定しません。
しかし、解決策を生み出すプロセスそのものを再現性のあるものにできれば、安定したビジネスを構築できます。
その答えは、テクノロジーの力を上手に活用すること にあります。
これこそが「ハイテク起業術」における「ハイテク」の意味するものです。
テクノロジー活用の誤解を解く ここで誤解のないように説明しておきます。
テクノロジーを活用するとは、AIを開発したり、難解なプログラムを組んだりすること ではありません。
そうではなく、
世の中には日本人がほとんど知らない便利なデジタルツールを活用
して経営の課題を解決するのです。
まさに、僕が派遣社員で勤務していた製造業の工場で、VRを使って作業マニュアルをつくり、トレーニングを効率化し、離職率を低減する改善活動を実施したのは、この「経営の課題×テクノロジーで解決」の公式に当てはまっているとお判りになるでしょう。
そして、その時に、自分の独力でVRコンテンツを開発するためのプログラムやシステムを開発するのではなく、安価で(ゼロ円~数万円)で、素人でも少し本気で勉強すれば使える海外の先進的なツールを見つけて活用した事も、お忘れなく。
例えば、日本で同じ仕組みを作るために専門業者を雇えば数百万円のコストがかかるようなものが、実はこのようなツールを使えば、その10分の1、100分の1のコストで実現できるのです。
しかも、パソコン初心者でも簡単に使えます。
例えば、今あなたが視聴している僕のオンライン授業ですが、ゼロからシステムを開発しようとすればシステム会社から数百万円のコストが請求されるでしょう。
しかし、私はteachableという海外ではメジャーなオンライン授業配信システムを活用する事で、毎月5千円前後のコストで、一切プログラミングを使用せず、管理者アカウントの開設からわずか数時間で、オンライン上で授業を配信する事ができるようになります。
つまり、私たちの役割は、経営者が知らないツールを活用し、問題を解決することです。
相手の知らないテクノロジーを使って課題を解決する事は「そろばんで膨大な計算をする人」に「電卓の存在」を教え、業務を効率化することに似ています。
毎日8時間かけて、仕事に必要な計算をそろばんで行っている経営者がいるとします。
電卓を使えばわずか5分で終わります。
その結果、1日あたり7時間55分の時間の人件費を削減できます。
一か月ではいくらでしょうか?1年間では?
そして、僕たちは、その削減できたコストの一部を報酬としてもらうのです。
これが、僕が最初に発見した「再現性のあるビジネス」の組み立て方です。
僕が最初に行った事業である、VR住宅展示場を活用した工務店の販売不振改善の事例使って、より具体的な方法をイメージしてみましょう。
解決すべき課題は、工務店の販売不振です。
これは非常にイメージしやすい課題ですね。
VRの住宅展示場というテクノロジーを使わない場合、従来の方法では次のような対策が考えられます。
新聞折込広告やポスティング、ホームページの作成、InstagramやYouTubeの広告出稿、 セールスマンを雇った販売活動などが考えられるでしょう。
しかし、これらの方法は他の協業他社も行っているし、相手の社長も日々、「ホームページをリニューアルしませんか?」「YouTube広告を始めませんか?」という営業を受けている状態です。
これでは、差別化が難しく、僕たちは仕事を売り込む事が難しいでしょう。
もし僕たちが、海外には初心者でも容易に作れるVR制作技術がある事を知らなければ、チラシの文言やホームページの内容、セールストークを少し変える程度の改善策しか提案できません。
しかし、VR住宅展示場を導入すれば、競合他社がまだ導入していないテクノロジーによる差別化が可能となります。
そしてそのVRテクノロジーに関して、なぜ海外で便利ツールが発達しているかと言えば、海外ではすでにVRが住宅販売に効果的であることが実証されており、導入する企業が多く、技術が普及しているからです。
その技術を日本向けにアレンジして提供することで、他社とは異なる販売促進システムを作ることができるわけです。
経営者にとって目新しいこの解決策は非常に魅力的で、多くの依頼を受けることができたのです。
しかも、これは僕が思いついた突飛なアイデアではなく、すでに海外で効果が証明された技術を応用したものなので、信頼性も高まりました。
その結果、VRを活用した販売促進サービスは、たった4ヶ月で1,000万円以上の売上を達成 できたのです。
この授業の最後に、もう一度要点を復習しましょう。
要点はこうです。
解決策をオリジナルで考えるのではなく、すでに海外で効果が実証済みのテクノロジーを活用する事。
以上です。
日本人経営者が知らない有効なツールを導入し、効果が実証された解決策として提案する事で、ほかの競合にはできない提案を簡単に行う事ができるようになります。
そして、「同じプロセス」で解決策を考案し続ける事で、再現性のあるビジネスモデルを育てていけるのです。
テクノロジーの「時差」が優位性を持続させる
経営者の課題を解決するためのテクノロジーには日本と海外で「時差」があります。
この時差を使い続ける限り、私たちは常に他者より有利に仕事を進める事ができるようになります。
あのコンサルタントはそんな事教えてくれなかった、
あの業者はそんな解決策提示してくれなかった、
そのように有利に仕事を進める事ができるようになります。
ここで重要なのは、いかにして「時差」を保ち続けるかという事です。
その方法はシンプルです。
常にアンテナを張っている事です。
もしあなたのライバルが、あなたが使っている海外のツールをマネして使っても、そのころには、あなたは次なるもっと便利なツールの情報を仕入れています。
それがアンテナの役割です。
あなたのライバルは、ツールだけ表面的にマネをする事はできても、あなたの情報源まで容易にまねる事はできないでしょう。
ここで、いくつかの情報源についてお伝えします。
- 海外のクラウドソージングサイト
- 海外の専門家YouTuber
- 海外の比較サイト
もちろん、これ以外にもありますが、これらの情報をチェックしているだけで、あなたの優位性は失われることはありません。
テクノロジーの時差を保ち続ける事ができます。
日本国内に存在する、子育てハイテク起業家のための「ブルーオーシャン」
さて、この記事の最後に、ダメ押しの強力な戦略をあなたにお伝えします。
これは、僕も意図せず発見したものなのですが、子育て世代のハイテク起業術には明確な「ブルーオーシャン」が存在します。
そのブルーオーシャンとは、「人口の少ない過疎地域の中小企業経営者」に照準を絞る事です。
なぜ、それが有効なのか?
その理由は、小さな田舎町ではそもそも「経営者の問題解決型」の人材がほとんどいません。
小さな田舎町では、経営者は経営の相談を商工会などに相談する事が多いですが、この商工会が紹介するのはたいてい「中小企業診断士」のような有資格者であり、補助金を取ったり融資のための事業計画を書くのは得意ですが、彼らは集客やセールスや採用の専門家ではありませんし、テクノロジーの実務家でもありません。
そして、集客や採用のコンサルタントがいたとしても、ほとんどの場合、ものすごくレベルの低い事しかできない自称コンサルタントで、実際はHPをつくるのが本業だったり、チラシをつくるのが本業だったりで、本質的な問題解決については技術を持ち合わせない人間だったりします。
だから、僕たちのように海外テクノロジーの時差を使って相手の問題を解決するという戦略を用いれば、ほとんどの場合、相手から選んでもらえます。
これは、一定以上の都会だとそうはいきいません。
しかし、田舎町では、いまだに「そろばん」以外の解決策に関する情報がなく、そこに「電卓」あるいは「パソコン」もっというと「AIによる自動計算」を持ち込むのですから、いかに有利に事を進められるかはイメージできるかと思います。
また、小さな町の小さな会社は当然ながら解決策のために用意できるコストも大きくありません。
ですが、海外のテクノロジーを活用する事で、他の解決策よりも圧倒的に小さなコストで実施できるため、導入してもらえる確率が高まります。
いくら海外で効果実証済みの解決策だからと言って、数百万円と数十万円では大きな違いがあります。
しかし、僕たち子育て世代のハイテク起業家にとっては、1つ数百万円の仕事を狙ういつ要はなく、数十万円でいいから、毎月安定して、自分の必要な仕事量が確保できれば良いのです。
もしあなたが移住、あるいは2拠点居住のライフスタイルに抵抗がなければ、まず人口5万人以下の町で経営者のつながりを作る事をお勧めします。
最後に、その具体的な方法についていくつかの僕が実践した方法を共有します。
- 地域の信用金庫に提案資料を持っていく
- 自治体に提案資料を持っていく
- 商工会に提案資料を持っていく
お気づきでしょうか?
これらは、全てこの授業の最初の方でお伝えした「隠れた資源を活用する」という原則に則っています。
地域の信用金庫の営業担当者は、日々地域の中小企業経営者と顔を合わせています。
彼らに、自分ができる事をA4用紙にまとめて、名刺を添えて渡します。
小さな町では、僕の言う「ハイテク起業家」のような尖った問題解決型の起業家はいません。
だから、10人資料を渡せば、1人か2人くらいは、あなたが特別な専門家である事に気が付きます。
小さな町でも、その一人か二人が持ってる経営者のつながりは数十人ではありません、数百人です。
あなたは十分に、そこから最初の仕事を得る可能性があります。
信用金庫の担当者も、経営者に対して有益な情報や人材を提供する事は、非常に大切な仕事なのです。
まずは、目の前の相手にあなたの事をしっかり理解してもらい、信頼に足る専門家である事を証明する事に全力を使いましょう。
そこで必要なのは、間違っても接待やなれ合いではありません。
あなたが提供できる解決策のサンプルを相手に理解できるような形で示す事です。
私の場合であれば、それがVRのコンテンツと、そのコンテンツがどんな問題をどのように解決するかを端的に記したA4の提案書でした。
自治体担当者も、商工会の担当者も、同じようにアプローチする事が可能です。
特に、小さな過疎の町の自治体であれば、現場の職員に提案するのではなく、町長、市長に直接あなたの事を売り込む事もお勧めします。
経営の課題を「地域活性の課題」と置き換えるのです。
行政に対してアプローチするポイントは、最初の案件はお金を生まなくても良いという事です。
行政はその仕組み上、すぐに予算を確保する事は困難です。
だから、最初は「最高の提案」を無料で行い、小さなプロジェクトを実施させてもらいます。
勉強会を開くというのはお勧めです。コストがほとんどかかりませんから。
そして、そこでの勉強会の様子を写真、動画に収録する事の許可を得て撮影させてもらいいます。
その撮影した素材こそが、あなたの「最初の報酬」となります。
行政と何らかの取り組みをしたという実績は、その地域であなたをプロモーションする際の強力な「信用証明書」になります。
田舎とはそういう場所なのです。
ちなみに私も、自分の今住んでいる岡山県備前市という人口3万人の消滅可能性都市と言われる田舎町で、最初にやった事は
「市長への直接プレゼン」です。
何が一番功を奏するかはやってみるまで分かりません。
ただ、これだけは言ます。
私が提案した方法に従って、あなたの最初の仕事を取るまでの具体的なアクションを最低10リストアップしてください。
あなたがそのすべてを実行し終わるよりも早く、最初の仕事が生まれている事でしょう。
もっとも重要なのは、まず行動を起こす事です。
健闘を祈ります。
椙原俊典(すぎはらとしみち)|360 ACADEMY